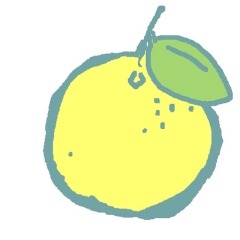2022-7-20 20:07
[utpr]夏の話07,オルフェウス
オルフェウスは竪琴の名手。
彼が奏でる音色は、神々も妖精も野獣も魅了した。
そして。
彼は森の木の妖精、エウリュディケと深く愛し合い、結んだ。
出会ったその瞬間に、これは運命だと歌が溢れる。
私の唯一無二。
しかし、運命とは残酷で、最愛の妻は婚礼の音色が消え去らぬうちに、毒蛇に噛まれて死んでしまう。
悲しみのオルフェウスは、エウリュディケを探し続けた。
冥神ハデスの元へ赴き、琴を弾きながら妻を返してほしいと頼んだ。
その旋律があまりにも美しく、ハデスは美しい音色の持ち主の願いを叶えた。
「だがよいな、太陽の光を仰ぐその時までけっして汝の妻の方へ振り返ってはならない。これが掟だ」
掟。
それさえ乗り越えれば。
彼は再び太陽の下で、最愛と愛し合うことを喜んだ。
この湧き出る愛の気持ちをどうしようか。
オルフェウスの喜びはどれほどのものか。
彼は妻の手を引いて冥府の道を引き返した。
ああしかし。
エウリュディケの手はなんと冷たく頼りないものか。
こんなにやせ細っていただろうか。
きっとやせ衰えてしまったのだろう。
こんなに枯れ枝のような手で。
あんなに柔らかく、陽だまりのような彼女の手が。
ああいや。
これは本当にエウリュディケなのか。
ハデスが欺いたのではないか。
そんなはずは、きっとない。
声を聴けばわかる
お前の花咲く声で私の名を呼んでくれ。
最愛の妻よ。
「エウリュディケ」
呼んでみても答えはない。
「エウリュディケ」
暗い冥界の道はどこまでつづくのか。
暗闇はーーー心をむしばんでいく。
握り返すこの感触のどこにも、最愛の彼女の面影が見えない。
この名前に、ため息でいい、答えてほしい。
エウリュディケ。
君と語り合いたいんだ。
私の問に答えないのか。
それとも、答えることができないのか。
君は本当に、君なのか?
疑心は闇にいざなわれる。
あの男は冥界の王。
死者を手放すわけがない。
そんなことはないと言ってくれ。
エウリュディケ。
エウリュディケ。
エウリュディケ。
嗚呼、オルフェウスは振り返ってしまった。
疑心に抗えなかった。
たった一言、ほんの一瞥でも良い。
彼女は最愛の妻なのか。
君だとわかる。
私の知るなにか一つでもあれば。
エウリュディケはそこにいた。
確かにそこにいた。
一瞬の永遠のようなその刹那、彼女のこの上なく悲しげな表情を最後に、冥界の闇に引き戻されてしまった。
「これが、琴座のオルフェウス。彼の物語です」
プラネタリウムにいるようだった。
四ノ宮さんの心地よいリズムと、紅茶の香りに満たされて、ここが寮の談話室であることを、忘れ去っていた。
しかし、何故彼らの話になったか。
話の発端は、全く別のことだった。
谷崎潤一郎の『春琴抄』についてだったが。
四ノ宮さんの語り部は続く。
彼はその後も、妻のエウリュディケ以外を愛することはなかった。彼女の面影だけを求め続けて歌う。
美しい詩を奏でるオルフェをものにしようという存在は沢山いました。それでも彼はエウリュディケの為の唄しか奏でません。それを良しとしなかったトラキアの女性たちに、石を投げつけられ、彼は絶命する。
「そこで彼は、地の底でようやく、エウリュディケとめぐりあって、愛を歌い続けられたのかもしれません
」
「振り返らずにいたら、このお話の面白みがなくなるんでしょうね」
「そうですね。彼女だとわかったら、太陽の光へたどり着けたと思います」
冥界の王は、求めるからこそ、得られない気持ちをよく知っている。冥界は、生きていたかった、なぜここにいるのだと嘆くものばかりだろう。
「そうだ!トキヤくん。目をつむってください」
夏の大三角形、ベガが有する星。
夜空に強く輝くその光には、愛の苦しみが込められていた。
届く光の中には、もう存在しない星の輝きもある。『あの点と点をつないで、よくこの形を思い浮かべるよね、昔の人って』
「僕は今、トキヤくんの手を握っています。これはボクの手です」
どうですか?
私の手より大きく、包み込む、少しひんやりとした四ノ宮さんの手のひら。「ボクの手は翔ちゃんの手よりずっと大きいんですよ」と、嬉しそうにいう。手には、少しだけ力が籠もり、熱を持った気がする。
四ノ宮さんにとっての翔が、特別なことが手を通じてわかる。
お互いの触れ合う場所が、熱を共有するように境界線をなくす。
私の温度が、四ノ宮さんの温度に溶けていく。
「まだ目を開けちゃ駄目ですよぉ」
そういって、一度四ノ宮さん手を離した。
演技の場以外で、手をつなぐことなど殆どない。こうやって繋がることに、戸惑いと、幾ばくかの喜びが押し寄せたが。それが虚空に消え去る。
「駄目だと言われると、目を開けたくなりますね」
「人はやっては駄目だと言われると、やりたくなることがあるんです。カリギュラ効果って言われていますね」
「駄目だと言われると、何が駄目なのか知りたくなるのは仕方ないと思います」
「ですよね。だからこそ、日本でも、鶴の恩返しのお話がありますし。見てはいけないですよ、って言われるとなおのこと、その対象への興味が湧く」
確かに、秘密があると、それを知りたくなる。ある種の探求欲。相手を知り尽くしたい、支配欲。どこにつながるかわからないが、抑制が抑揚の原因となることを、どうして人は避けられないのか。
「隣人を愛せよ。自分を愛するように、隣人も愛することができれば、きっと、世界はもっと素敵です。でも、もし。隣人を愛するな、敵と思えと言われても、きっと、愛するのと同じように、隣人を思うでしょう」
その言葉に、同室の騒がしい赤色がちらつく。
「自分を愛するなと言われると、自分のどこを愛していたか気づく。これらすべてがいけないとはいいません。抑制が気づくきっかけになることもある、はずです」
「そう、でしょうか……」
「言葉ではわかっているつもりなんですけど。難しいですね……」
振り向いてはいけないと言われて、エウリュディケがどんな人だったか、もっとずっと考えてしまったのではないでしょうか。
「それでは、トキヤくん。手を失礼しますね」
先程より温かく、ぎこちない手の握り方。
保湿のされていない、少しカサついた手のひら。
なにより、柔らかい部分が違う。
弦を扱う人の、固くなった指先。
琴は弦楽器。指先で感じる楽器。
だからこそ、手先まで、その相手への思いが詰まっているのかもしれないです。
弦を、指で弾くとき、その音は、陽気なときも、時折苦しみもあって……。
「これは……。ちがう……」
ビクッと小さく手が震えた。
スッと息を吸い込む音。僅かな音。
その音を聞いた途端、どうしても一人だけ思い浮かぶ。
これは、脊髄からのシグナルどおりに言えば、嫌な予感に近いのだ。
その相手でなければ良いという人物が一人。
隣人、脳裏をよぎった赤が、頭の中を埋め尽くす。
彼の奏でる指先が表す心。どれをとっても真っ直ぐな音。
「音也?」
薄く目を開いた先に、驚く顔が見える。
それからすぐに、顔が綻ぶ。
「なんでわかったの!?」
ぎゅっとこちらの手を握り返す。まるで見つけてくれたことが嬉しいように。指先から感じる高揚。
「流れとして、違うものを掴まされる気はしていましたから。……そもそも何故あなたがここにいるんですか」
「二人で向かい合って手を握っているからさぁ、何事かと思って」
「ボクがトキヤくんの手をぎゅーってしてたところからですね」
談話室に顔を出したら、私達の姿を見て何事かと思ったらしい。
「そーそー。トキヤが顔伏せてたから、何か悩み事かと思ったけど。そうじゃなかったんだね!」
悩み事は今目の前に居ますよ。
当人は「よかったー!」と、安堵するもつかの間、「どしてどうして?」と、手を強く握りながら喜色満面。矢継ぎ早の行き来に、いつもの、慣れてしまいそうになる騒がしさが、降り注ぐ。
それこそ直感だとしか告げることができない。
「もしかしたら、エウリュディケが答えなかったのは、こういうことかもしれないって、思ったことがあるんです。ハデスなら、エウリュディケにも、何かを与えたかもしれません」
四ノ宮さんの言葉に、なんのこと?と疑問符を浮かべる音也。
「これはオルフェウスの物語であって、果たしてエウリュディケはどう思っていたのでしょうね。彼女も、オルフェウスと一緒に生きることを望んだのなら、彼女にも掟があったかもしれない」
それは、振り向かないオルフェウスの背だけを見続けることか。答えてはいけないということか。
それもきっと苦しかっただろう。
姿が見えないことは、良いことも悪いことも、想像できてしまうんです。そこに居ない、それだけで、どうとでも思い描ける。それが物語にもなるんです。
愛を思い描くだけで、物語は生まれる。
「少なくとも、この手が音也くんと思ったのは、トキヤくんが音也くんのことを思い浮かべたんですね」
「な……っ。いえ、この妙に乾いた手は、たしかに、ケアの足りていない手で思い当たるフシが一つしか無いのは、ええ、否定しませんが」
「そこで!?」
「四ノ宮さんの手を握ってみなさい」
「那月の手〜あったかーい!」
「音也くんの手は優しいですね」
「情報の80%は目から得るものだと言われています。もちろん生まれつき目が見えない人も居ます。でも、見える人にとっての、トキヤくんの20%に、音也くんはちゃんといるんですね」
「だよね!だってトキヤ俺のこといつも見てるもん」
「見ていません」
「えーだって、目で追ったら目が合うじゃん」
「見ていませんたまたまです」
「きっと、音也くんはトキヤくんの佐助になれますよ」
「いやですよ、この男に委ねるのは」
「なんのこと?」
2度目の疑問符が、赤毛の上に浮かんで見える。
本当に、オルフェウスの立場になったときに、エウリュディケの存在が、自分にはわかるのだろうか。
そう考えようにも、最愛の存在が、目の前の騒がしい男に書き換えられそうになるのを、思考から振り払う。
20%の感覚すら奪ってくるこの男との付き合いは、これからももっとずっと長く続くのだから。
.
オルフェウス神話については、阿刀田高著『ギリシャ神話を知っていますか』を参考にしています。
谷崎潤一郎『春琴抄』については、ちょっと力不足でこの場に盛り込めませんでした。
名残だけおいています。
前の記事へ
次の記事へ
カレンダー
カテゴリー
アーカイブ
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(4)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(2)
- 2023年12月(1)
- 2023年11月(2)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(8)
- 2023年8月(1)
- 2023年7月(5)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(1)
- 2023年3月(13)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(3)
- 2022年10月(3)
- 2022年9月(1)
- 2022年7月(11)
- 2022年6月(3)
- 2022年5月(15)
- 2022年4月(5)
- 2022年3月(1)
- 2022年2月(5)
- 2022年1月(3)
- 2021年8月(5)
- 2021年6月(3)
- 2021年4月(6)
- 2021年3月(4)
- 2021年1月(3)
- 2020年11月(2)
- 2020年9月(2)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年5月(2)
- 2020年4月(4)
- 2020年3月(5)
- 2020年2月(6)
- 2020年1月(1)
- 2019年12月(9)
- 2019年10月(1)
- 2019年9月(4)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(7)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(1)
- 2018年9月(3)
- 2018年8月(6)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(8)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(9)
- 2018年1月(2)
- 2017年12月(13)
- 2017年11月(1)
- 2017年10月(7)
- 2017年9月(7)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(12)
- 2017年6月(5)
- 2017年5月(9)
- 2017年4月(9)
- 2017年2月(6)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(3)
- 2016年10月(8)
- 2016年9月(1)
- 2016年8月(1)
- 2016年7月(5)
- 2016年6月(7)
- 2016年5月(6)
- 2016年3月(14)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年12月(4)
- 2015年9月(12)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(8)
- 2015年5月(10)
- 2015年4月(7)
- 2015年3月(4)
- 2015年2月(3)
- 2015年1月(1)
- 2014年12月(7)
- 2014年11月(3)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(8)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(6)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(5)
- 2014年2月(5)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(3)
- 2013年11月(4)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(5)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(9)
- 2013年5月(3)
- 2013年4月(4)
- 2013年3月(6)
- 2013年2月(8)
- 2013年1月(7)
- 2012年12月(6)
- 2012年11月(6)
- 2012年10月(12)
- 2012年9月(7)
- 2012年8月(16)
- 2012年7月(8)
- 2012年6月(10)
- 2012年5月(8)
- 2012年4月(8)
- 2012年3月(7)
- 2012年2月(13)
- 2012年1月(11)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(12)
- 2011年10月(12)
- 2011年9月(5)
- 2011年8月(6)
- 2011年7月(10)
- 2011年6月(10)
- 2011年5月(12)
- 2011年4月(10)
- 2011年3月(7)
- 2011年2月(17)
- 2011年1月(8)
- 2010年12月(5)
- 2010年11月(11)
- 2010年10月(13)
- 2010年9月(2)
- 2010年8月(15)
- 2010年7月(10)
- 2010年6月(9)
- 2010年5月(8)
- 2010年4月(10)
- 2010年3月(15)
- 2010年2月(11)
- 2010年1月(24)
- 2009年12月(15)
- 2009年11月(22)
- 2009年10月(13)
- 2009年9月(10)
- 2009年8月(2)
- 2009年7月(18)
- 2009年6月(12)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(9)
- 2009年3月(13)
- 2009年2月(12)
プロフィール
| 性 別 | 女性 |
| 誕生日 | 6月14日 |